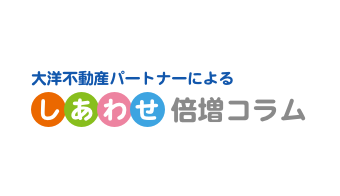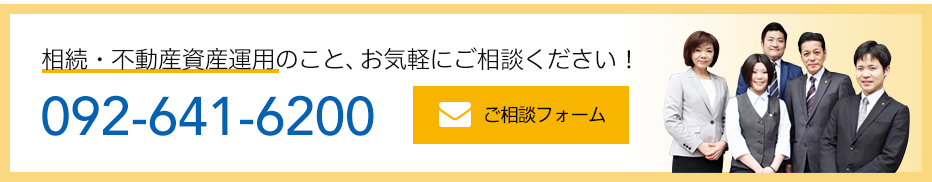2025/11/10
人生100年時代の働き方~仕事と介護の両立~
「介護離職」って、聞いたことはありますか?
親や配偶者など、家族の介護が必要になったとき、仕事との両立が難しくなり、やむを得ず仕事を辞める方が増えているそうです。
みなさんの周りでも家族の介護に携わっている話など耳にする機会が増えてきているのではないでしょうか。
今回は、「介護離職」という選択を迫られる前に、知っておきたい制度や支援について、私の体験も交えながらお話しできればと思います。

1 「介護離職」は増えている!?
厚生労働省の調査によると、年間約10万人が介護を理由に離職していると言われていて、特に50代の方の離職が多いようです。
離職に至る背景には、「仕事を休みたくても、代わりをお願いできる体制が整っていない」「休みを申請しづらい」といった職場環境の課題もあるようです。
離職後は収入が減少しますし、介護が必要なくなってからの再就職も簡単ではなく、社会とのつながりが希薄になることなども懸念されます。
2 介護離職を防ぐために知っておきたいこと
介護が必要になったとき、「仕事を辞めるしかない」と思い詰めてしまう前に、使える制度や相談できる窓口があることを知っておくことがとても大事です。
ここでは、仕事と介護の両立を支える主な制度等をご紹介します。
◆介護休業制度
要介護状態の家族を介護するために、対象家族1人につき3回まで最大93日間の休業が取得できます。分割して取得することも可能で一定の条件を満たせば、雇用保険の「介護休業給付金」が受け取れます。
◆介護休暇制度
対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで、1日または時間単位で取得できる休暇制度です。
病院の付き添いや介護サービスの手続きなどにも活用できます。
◆短時間勤務等の制度
企業によって異なりますが、「短時間勤務」「フレックス」「時差出勤」など、勤務時間を柔軟に調整できる制度を導入している場合があります。
通院の付き添いや介護サービスの時間に合わせた働き方も可能になってきます。
◆時間外労働の制限
労働者からの申し出で介護終了まで残業が免除されます。
◆地域包括支援センター
介護に関する相談窓口として、市区町村に設置されています。
介護保険制度の説明、サービスの紹介や仕事との両立の悩みなど幅広い相談にのってくれます。

3 働き方の見直しと企業の取り組み
出産や育児に関する制度は少しずつ浸透してきましたが、介護についてはまだまだ「知らない」「分からない」と感じている方が多いのではないでしょうか。
そんな中、2025年4月に「育児・介護休業法」が改正され、事業主に対して、仕事と介護の両立支援制度などの申出が円滑に行われるよう、雇用環境の整備が義務づけられました。
仕事と介護の両立を支えるためには、制度だけでなく、職場の理解や働き方の柔軟性も欠かせないと思います。
最近では、企業側の取り組みも少しずつ進んできているようです。
《仕事と介護の両立支援制度の整備》
支援や制度を活用せずに退職するのを防ぐために、介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供が義務づけられています。
また、テレワークの導入や時短勤務などの制度を社内で整備し、社員が安心して相談できる体制を整える企業も増えています。
《社内での情報共有や仲間とのつながり》
介護に関する知識や制度の理解が広がることで、同じような立場の社員同士が情報を共有できたり、悩みを話せる場があることで、社員が相談しやすい雰囲気づくりにもつながります。

4 終わりに
「自分にはまだ関係ないかな」と思っていても、介護はある日突然やってくることがあります。
私自身も、まさか…というタイミングで家族の体調が急に悪くなり、仕事との両立に悩んだ経験があります。
だからこそ、「その時」に備えて、制度や支援の存在を知っておくことが大切です。
「介護が始まったら、仕事を辞めるしかない」と思い込まず、まずは職場の上司や人事担当者、また自治体の専門である「地域包括支援センター」に相談してみましょう。
相談することで選択肢が広がり、私自身も仕事を続けながら家族を支える道を見つけることができました。
このコラムが掲載される11月には、11月11日の「介護の日」があり、各地でイベントも開催されるようです。この機会に、介護を少し身近に感じていただけたらと思います。
「介護離職」って、聞いたことはありますか?
親や配偶者など、家族の介護が必要になったとき、仕事との両立が難しくなり、やむを得ず仕事を辞める方が増えているそうです。
みなさんの周りでも家族の介護に携わっている話など耳にする機会が増えてきているのではないでしょうか。
今回は、「介護離職」という選択を迫られる前に、知っておきたい制度や支援について、私の体験も交えながらお話しできればと思います。

1 「介護離職」は増えている!?
厚生労働省の調査によると、年間約10万人が介護を理由に離職していると言われていて、特に50代の方の離職が多いようです。
離職に至る背景には、「仕事を休みたくても、代わりをお願いできる体制が整っていない」「休みを申請しづらい」といった職場環境の課題もあるようです。
離職後は収入が減少しますし、介護が必要なくなってからの再就職も簡単ではなく、社会とのつながりが希薄になることなども懸念されます。
2 介護離職を防ぐために知っておきたいこと
介護が必要になったとき、「仕事を辞めるしかない」と思い詰めてしまう前に、使える制度や相談できる窓口があることを知っておくことがとても大事です。
ここでは、仕事と介護の両立を支える主な制度等をご紹介します。
◆介護休業制度
要介護状態の家族を介護するために、対象家族1人につき3回まで最大93日間の休業が取得できます。分割して取得することも可能で一定の条件を満たせば、雇用保険の「介護休業給付金」が受け取れます。
◆介護休暇制度
対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで、1日または時間単位で取得できる休暇制度です。
病院の付き添いや介護サービスの手続きなどにも活用できます。
◆短時間勤務等の制度
企業によって異なりますが、「短時間勤務」「フレックス」「時差出勤」など、勤務時間を柔軟に調整できる制度を導入している場合があります。
通院の付き添いや介護サービスの時間に合わせた働き方も可能になってきます。
◆時間外労働の制限
労働者からの申し出で介護終了まで残業が免除されます。
◆地域包括支援センター
介護に関する相談窓口として、市区町村に設置されています。
介護保険制度の説明、サービスの紹介や仕事との両立の悩みなど幅広い相談にのってくれます。

3 働き方の見直しと企業の取り組み
出産や育児に関する制度は少しずつ浸透してきましたが、介護についてはまだまだ「知らない」「分からない」と感じている方が多いのではないでしょうか。
そんな中、2025年4月に「育児・介護休業法」が改正され、事業主に対して、仕事と介護の両立支援制度などの申出が円滑に行われるよう、雇用環境の整備が義務づけられました。
仕事と介護の両立を支えるためには、制度だけでなく、職場の理解や働き方の柔軟性も欠かせないと思います。
最近では、企業側の取り組みも少しずつ進んできているようです。
《仕事と介護の両立支援制度の整備》
支援や制度を活用せずに退職するのを防ぐために、介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供が義務づけられています。
また、テレワークの導入や時短勤務などの制度を社内で整備し、社員が安心して相談できる体制を整える企業も増えています。
《社内での情報共有や仲間とのつながり》
介護に関する知識や制度の理解が広がることで、同じような立場の社員同士が情報を共有できたり、悩みを話せる場があることで、社員が相談しやすい雰囲気づくりにもつながります。

4 終わりに
「自分にはまだ関係ないかな」と思っていても、介護はある日突然やってくることがあります。
私自身も、まさか…というタイミングで家族の体調が急に悪くなり、仕事との両立に悩んだ経験があります。
だからこそ、「その時」に備えて、制度や支援の存在を知っておくことが大切です。
「介護が始まったら、仕事を辞めるしかない」と思い込まず、まずは職場の上司や人事担当者、また自治体の専門である「地域包括支援センター」に相談してみましょう。
相談することで選択肢が広がり、私自身も仕事を続けながら家族を支える道を見つけることができました。
このコラムが掲載される11月には、11月11日の「介護の日」があり、各地でイベントも開催されるようです。この機会に、介護を少し身近に感じていただけたらと思います。
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。