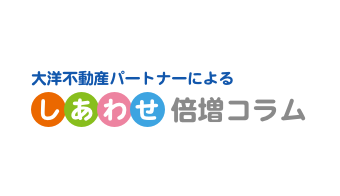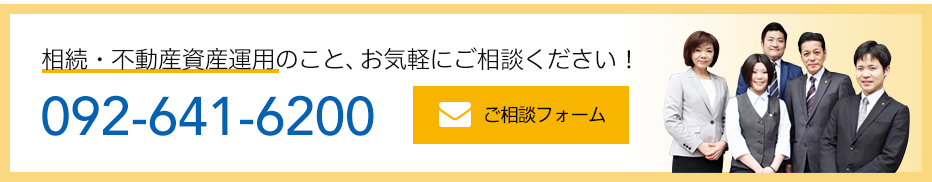2025/01/10
相続人が相続を放棄することはできるか?
Q 父が亡くなりました。
残されたのは母と私と兄の3人です。父の遺産は、現在わかっている範囲では、築後50年も経過した自宅と若干の預貯金があるだけのようです。
先日、金融会社から、借金の支払いの督促通知が届きました。私としては、老朽化した自宅を引き継ぐ気持ちはありませんし、借金の返済に追われるのも煩わしく感じています。
私は、法律上は父の相続人の一人ですが、父の財産も借金も相続したいとは思っておりません。
相続人が、借金を免れるために相続を放棄することは法律上可能なのでしょうか。
その場合、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?

1 相続開始後の相続人の権利
民法は、相続の一般的効力として、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務承継する。」(民法第898条本文)と定めています。
つまり、相続人は、被相続人(御父様)が有していた権利だけではなく、被相続人が負担していた義務(借金の返済義務、物の引渡義務等)も一緒に承継することになります。
基本的に権利の放棄は、その権利者に不利益なことではあっても、他人に迷惑をかけることではありませんから自由にできるはずですが、義務の放棄は債権者にとっては迷惑な話なので、原則として債権者の同意がなければできないはずです。
しかし、相続においては、相続人は相続の放棄をすることが認められています。

2 相続放棄の方式
相続の放棄は、ただ単に相続を放棄すると宣言しても効果は認められません。
民法では、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」(民法第938条)と定めています。
ご自分が相続を放棄する旨を述べた相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すればよいのです。
ただし、相続の放棄ができるには期限が限られています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」(民法第915条)と定められているからです。
したがって、相続を放棄しようとする場合は、相続が開始した(御父様が逝去された)こと、自分がその相続人であることを知った日(通常、自分が父親の子であることは既に知っていますので、実際上は相続が開始した日と同一になる場合が殆どだと思います。)から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。

3 相続放棄の効力
相続放棄の効力については、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法第939条)と定められていますので、被相続人の財産を引き継がないと同時に、被相続人の借金等の債務も一切引き継がないことになります。
4 相続放棄をする場合に留意すべき事項
1つには、相続放棄は、被相続人の借金を引き継がないし、遺産分割協議の面倒からも解放されるという面はありますが、撤回することができないという点に留意が必要です。
相続を放棄すると、その後に新たに被相続人の借金を上回る多額の財産が見つかったとしても、相続の放棄は撤回できませんので、その遺産の分配を受けることはできません。
2つに、そもそも、相続の放棄は、3箇月以内に行わなければなりませんので、遺産の十分な調査が出来ていない場合もあり得ます。
ほかに遺産が存在するかもしれないというときは、家庭裁判所に、3箇月という期間では遺産の調査が十分にできなかったこと等を示して、3箇月という期間を伸長してもらうよう申立てをすることが必要です。
ただし、この申立ては当初の、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内にする必要がありますので、この点もご留意ください。 以 上
Q 父が亡くなりました。
残されたのは母と私と兄の3人です。父の遺産は、現在わかっている範囲では、築後50年も経過した自宅と若干の預貯金があるだけのようです。
先日、金融会社から、借金の支払いの督促通知が届きました。私としては、老朽化した自宅を引き継ぐ気持ちはありませんし、借金の返済に追われるのも煩わしく感じています。
私は、法律上は父の相続人の一人ですが、父の財産も借金も相続したいとは思っておりません。
相続人が、借金を免れるために相続を放棄することは法律上可能なのでしょうか。
その場合、どのような要件を満たせばよいのでしょうか?

1 相続開始後の相続人の権利
民法は、相続の一般的効力として、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務承継する。」(民法第898条本文)と定めています。
つまり、相続人は、被相続人(御父様)が有していた権利だけではなく、被相続人が負担していた義務(借金の返済義務、物の引渡義務等)も一緒に承継することになります。
基本的に権利の放棄は、その権利者に不利益なことではあっても、他人に迷惑をかけることではありませんから自由にできるはずですが、義務の放棄は債権者にとっては迷惑な話なので、原則として債権者の同意がなければできないはずです。
しかし、相続においては、相続人は相続の放棄をすることが認められています。

2 相続放棄の方式
相続の放棄は、ただ単に相続を放棄すると宣言しても効果は認められません。
民法では、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」(民法第938条)と定めています。
ご自分が相続を放棄する旨を述べた相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すればよいのです。
ただし、相続の放棄ができるには期限が限られています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」(民法第915条)と定められているからです。
したがって、相続を放棄しようとする場合は、相続が開始した(御父様が逝去された)こと、自分がその相続人であることを知った日(通常、自分が父親の子であることは既に知っていますので、実際上は相続が開始した日と同一になる場合が殆どだと思います。)から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。

3 相続放棄の効力
相続放棄の効力については、「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法第939条)と定められていますので、被相続人の財産を引き継がないと同時に、被相続人の借金等の債務も一切引き継がないことになります。
4 相続放棄をする場合に留意すべき事項
1つには、相続放棄は、被相続人の借金を引き継がないし、遺産分割協議の面倒からも解放されるという面はありますが、撤回することができないという点に留意が必要です。
相続を放棄すると、その後に新たに被相続人の借金を上回る多額の財産が見つかったとしても、相続の放棄は撤回できませんので、その遺産の分配を受けることはできません。
2つに、そもそも、相続の放棄は、3箇月以内に行わなければなりませんので、遺産の十分な調査が出来ていない場合もあり得ます。
ほかに遺産が存在するかもしれないというときは、家庭裁判所に、3箇月という期間では遺産の調査が十分にできなかったこと等を示して、3箇月という期間を伸長してもらうよう申立てをすることが必要です。
ただし、この申立ては当初の、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内にする必要がありますので、この点もご留意ください。 以 上
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。