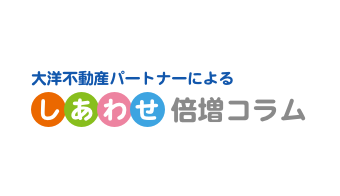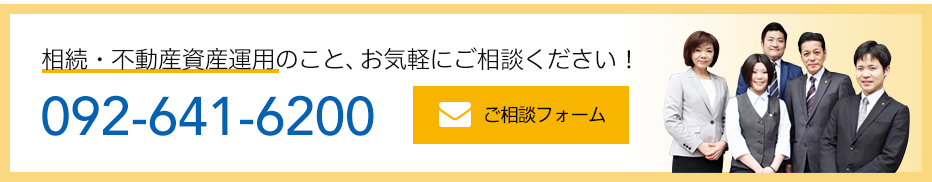2025/10/10
伊勢と出雲は本当は仲がいい
今月は、私自身が企画し取り仕切ることになった特別な催しについてご紹介させていただきたい。
二條家による出雲大社への献上が意味するもの
令和7年9月29日、北島国造館と出雲大社において、藤原五摂家の一つである二條家が香を献じる「二社奉納」の行事が執り行われる。
これは、伝統ある二條家と縁深い香道桜月流と舞の奉納が一体となった特別な機会である。
伊勢に連なる家柄が出雲の大社に香を献じるというのは、単なる儀式を超えた意味を持っているように私には思える。
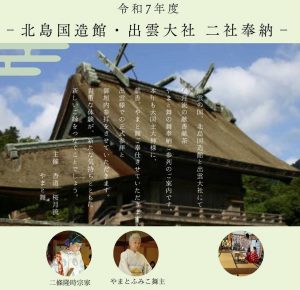
そもそも「伊勢と出雲は仲が悪い」という言い方をされることがある。
天照大神を祀る伊勢神宮と、大国主大神を祀る出雲大社。
神話の中で国譲りの場面があるため、「勝者と敗者」という図式で語られることが多い。
しかし、よくよく神話を読み直すと、それは対立の物語ではなく、むしろ「役割の分担」であったことがわかる。
国譲りは出雲の敗北、しかし...
その国譲りの際に描かれる象徴的な場面の一つが、建御名方神と建御雷神の決闘である。
大国主大神の子である建御名方神は、父の国を譲り渡すことに反発し、天照大神の使者である建御雷神に力比べを挑んだ。
両神は腕力で組み合い、海や山を揺るがすほどの戦いとなったと伝えられる。だが最終的には建御名方神が押さえ込まれ、敗北を認めて信濃へ退いた。
この場面だけを切り取れば、まさに「出雲の敗北」とも見える。
しかし注目すべきは、建御名方神が討たれずに「生かされた」という点である。
命を奪われるのではなく、新たな役割を与えられ信濃に鎮まった。
これは単なる勝敗ではなく、「力を競った上で互いの存在を尊重しつつ役割を分ける」という日本的な解決法の象徴だと言える。
伊勢と出雲の関係もまさにこれと同じで、勝ち負けの話ではなく、分担と調和の物語なのだ。

補い合い日本を支える
実際、今も出雲大社では「国造りの神」として大国主が祀られ、人々の縁を結ぶ神として厚い信仰を集めている。
一方で伊勢神宮は「日本の総氏神」として、天皇を中心とした祈りの場になっている。
両者が担っている領域は違うが、決して相反するものではない。
むしろ補い合って日本を支えてきたと見るべきではないだろうか。
今回の奉納行事は、その「両輪の関係」を現代に示すもののように感じている。
二條家といえば、かつて藤原氏の中枢として朝廷を支え、文化と礼法の伝統を継いできた家柄である。
その家が伊勢の系譜を背に出雲大社へと赴き、香を献じる。
この出来事自体が「伊勢と出雲は対立する存在ではない」ということを、静かに、しかし力強く物語っているのではないだろうか。

役割分担と調和
私たちの日常に置き換えても学ぶべきことがある。
家庭や職場でも、人それぞれ役割が違う。
違うからこそ衝突もあるが、本来は補い合う関係にあるはずだ。
伊勢と出雲の関係を思えば、その違いは争いの種ではなく、全体を成り立たせる両輪だと考えることができる。
伊勢の香と出雲の祈り。
その二つが交わる場に立ち会えることを、私は大きな喜びと感じている。
読者の皆さまにも、この行事をきっかけに「伊勢と出雲は本当は仲が良い」ということを改めて思い出していただければ幸いだ。
今月は、私自身が企画し取り仕切ることになった特別な催しについてご紹介させていただきたい。
二條家による出雲大社への献上が意味するもの
令和7年9月29日、北島国造館と出雲大社において、藤原五摂家の一つである二條家が香を献じる「二社奉納」の行事が執り行われる。
これは、伝統ある二條家と縁深い香道桜月流と舞の奉納が一体となった特別な機会である。
伊勢に連なる家柄が出雲の大社に香を献じるというのは、単なる儀式を超えた意味を持っているように私には思える。
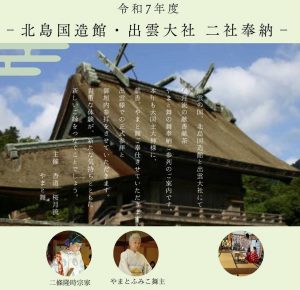
そもそも「伊勢と出雲は仲が悪い」という言い方をされることがある。
天照大神を祀る伊勢神宮と、大国主大神を祀る出雲大社。
神話の中で国譲りの場面があるため、「勝者と敗者」という図式で語られることが多い。
しかし、よくよく神話を読み直すと、それは対立の物語ではなく、むしろ「役割の分担」であったことがわかる。
国譲りは出雲の敗北、しかし...
その国譲りの際に描かれる象徴的な場面の一つが、建御名方神と建御雷神の決闘である。
大国主大神の子である建御名方神は、父の国を譲り渡すことに反発し、天照大神の使者である建御雷神に力比べを挑んだ。
両神は腕力で組み合い、海や山を揺るがすほどの戦いとなったと伝えられる。だが最終的には建御名方神が押さえ込まれ、敗北を認めて信濃へ退いた。
この場面だけを切り取れば、まさに「出雲の敗北」とも見える。
しかし注目すべきは、建御名方神が討たれずに「生かされた」という点である。
命を奪われるのではなく、新たな役割を与えられ信濃に鎮まった。
これは単なる勝敗ではなく、「力を競った上で互いの存在を尊重しつつ役割を分ける」という日本的な解決法の象徴だと言える。
伊勢と出雲の関係もまさにこれと同じで、勝ち負けの話ではなく、分担と調和の物語なのだ。

補い合い日本を支える
実際、今も出雲大社では「国造りの神」として大国主が祀られ、人々の縁を結ぶ神として厚い信仰を集めている。
一方で伊勢神宮は「日本の総氏神」として、天皇を中心とした祈りの場になっている。
両者が担っている領域は違うが、決して相反するものではない。
むしろ補い合って日本を支えてきたと見るべきではないだろうか。
今回の奉納行事は、その「両輪の関係」を現代に示すもののように感じている。
二條家といえば、かつて藤原氏の中枢として朝廷を支え、文化と礼法の伝統を継いできた家柄である。
その家が伊勢の系譜を背に出雲大社へと赴き、香を献じる。
この出来事自体が「伊勢と出雲は対立する存在ではない」ということを、静かに、しかし力強く物語っているのではないだろうか。

役割分担と調和
私たちの日常に置き換えても学ぶべきことがある。
家庭や職場でも、人それぞれ役割が違う。
違うからこそ衝突もあるが、本来は補い合う関係にあるはずだ。
伊勢と出雲の関係を思えば、その違いは争いの種ではなく、全体を成り立たせる両輪だと考えることができる。
伊勢の香と出雲の祈り。
その二つが交わる場に立ち会えることを、私は大きな喜びと感じている。
読者の皆さまにも、この行事をきっかけに「伊勢と出雲は本当は仲が良い」ということを改めて思い出していただければ幸いだ。
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。