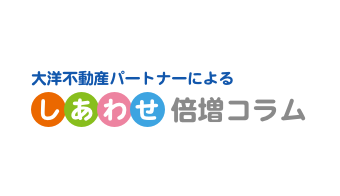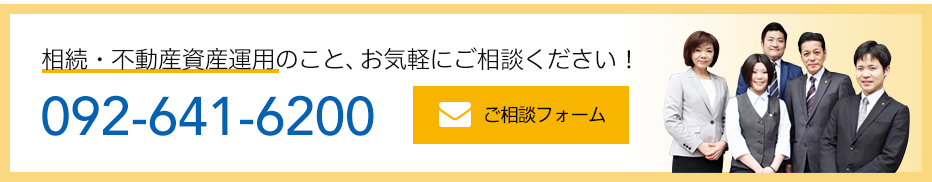2025/10/10
給付付き税額控除について
「給付付き税額控除」という言葉を、過去に何度か耳にされてきたことと思います。
最近、自由民主党、公明党、立憲民主党の3党が協議を開始することで合意したとのことで、今度こそ実現するのでは?という機運がにわかに高まっています。
政権が盤石ではないといろいろなことが起こり得ますね。
では、実際に「給付付き税額控除」と聞いて、その仕組みを理解できている方がどれくらいいらっしゃるかというと、そこまで多くはいらっしゃらないと思います。
そこで今回は、「給付付き税額控除」について少し確認していきましょう。

(1)背景
長引く物価上昇により、所得が低い方の生活が厳しくなっています。
所得が低い方は、自身の収入に占める生活必需品(食料品や光熱費他)への支出割合が高いので、物価高の影響を強く受けます。
また、生活必需品等に課されている消費税も、やはり所得が低い方ほど負担割合が高くなります(消費税の「逆進性」と呼ばれています)。
また、これまで、コロナ禍や物価高騰対策として、全国民への給付金の一律支給や所得が低い方への給付金支給が実施されてきましたが、それにかかる事務作業の多大な手間やコスト、充分な効果が得られているかが不明瞭、などといった課題がありました。
去年の定額減税についても好評だったとは言い難いです。

(2)仕組み
以上のようなことを鑑み、「給付と減税をセットで行う」というのが「給付付き税額控除」です。
税額控除、というのはいったん計算して出た所得税額から、直接控除することを言います。
例えば、払うべき税額が3万円で税額控除が5万円だとしましょう。通常は払うべき税額が上限となり税額控除するので2万円は引けずに終わってしまいます。
「給付付き税額控除」は、この引けずに終わった2万円を現金で支給する、という仕組みです。
納税額が少ない人や、納税額が無い人でもお金を支給してもらえる、という仕組みです。
これにより公平性が実現できる、というものです。
雑感
自由民主党の総裁選挙が10月4日に行われる予定です(この原稿を書いているのは9月下旬です)。
世間の予想通り、5人の議員が立候補しました。
9月下旬現在、所信発表演説会に始まり、様々な討論会が予定されています。
このコラムが公開される頃には新しい総裁が誕生していることでしょう。

「給付付き税額控除」はこれまでも浮かんでは消えていった施策でした。
果たして実現するのでしょうか?
実現するとしても「年末調整で?」それとも「確定申告で?」はたまた「去年の定額減税のように市町村に頑張ってもらうの?」と、どの段階で行うのか、という一つをとっても、事務作業の構築が大変そうです。
新しく誕生した新総裁が何を実行するにしても、最優先は、日本国民が少しでも安心して安全に幸せに暮らせることですよね。
「給付付き税額控除」という言葉を、過去に何度か耳にされてきたことと思います。
最近、自由民主党、公明党、立憲民主党の3党が協議を開始することで合意したとのことで、今度こそ実現するのでは?という機運がにわかに高まっています。
政権が盤石ではないといろいろなことが起こり得ますね。
では、実際に「給付付き税額控除」と聞いて、その仕組みを理解できている方がどれくらいいらっしゃるかというと、そこまで多くはいらっしゃらないと思います。
そこで今回は、「給付付き税額控除」について少し確認していきましょう。

(1)背景
長引く物価上昇により、所得が低い方の生活が厳しくなっています。
所得が低い方は、自身の収入に占める生活必需品(食料品や光熱費他)への支出割合が高いので、物価高の影響を強く受けます。
また、生活必需品等に課されている消費税も、やはり所得が低い方ほど負担割合が高くなります(消費税の「逆進性」と呼ばれています)。
また、これまで、コロナ禍や物価高騰対策として、全国民への給付金の一律支給や所得が低い方への給付金支給が実施されてきましたが、それにかかる事務作業の多大な手間やコスト、充分な効果が得られているかが不明瞭、などといった課題がありました。
去年の定額減税についても好評だったとは言い難いです。

(2)仕組み
以上のようなことを鑑み、「給付と減税をセットで行う」というのが「給付付き税額控除」です。
税額控除、というのはいったん計算して出た所得税額から、直接控除することを言います。
例えば、払うべき税額が3万円で税額控除が5万円だとしましょう。通常は払うべき税額が上限となり税額控除するので2万円は引けずに終わってしまいます。
「給付付き税額控除」は、この引けずに終わった2万円を現金で支給する、という仕組みです。
納税額が少ない人や、納税額が無い人でもお金を支給してもらえる、という仕組みです。
これにより公平性が実現できる、というものです。
雑感
自由民主党の総裁選挙が10月4日に行われる予定です(この原稿を書いているのは9月下旬です)。
世間の予想通り、5人の議員が立候補しました。
9月下旬現在、所信発表演説会に始まり、様々な討論会が予定されています。
このコラムが公開される頃には新しい総裁が誕生していることでしょう。

「給付付き税額控除」はこれまでも浮かんでは消えていった施策でした。
果たして実現するのでしょうか?
実現するとしても「年末調整で?」それとも「確定申告で?」はたまた「去年の定額減税のように市町村に頑張ってもらうの?」と、どの段階で行うのか、という一つをとっても、事務作業の構築が大変そうです。
新しく誕生した新総裁が何を実行するにしても、最優先は、日本国民が少しでも安心して安全に幸せに暮らせることですよね。
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。