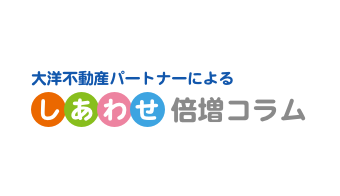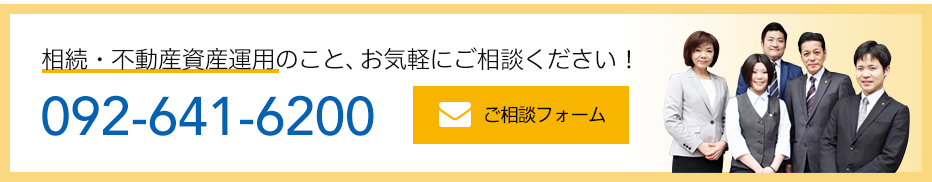2025/05/10
第18回 依存と依存症について
「依存」と聞くと、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか。
もしかすると、ネガティブな印象を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。
デジタル大辞泉によれば、「依存」とは「他に頼って存在、または生活すること」と定義されています。実際、私たちは日常生活の中で多くのものに依存しています。
例えば、私はこの原稿を書くのにパソコンを使っていますし、視力が低いためメガネをかけています。
原稿のやり取りはメールを利用し、執筆中にはインターネットで調べ物をしています。
これらはすべて、私がさまざまなツールや技術に依存している例です。
依存と自立は対立しない
障害者研究の第一人者である熊谷晋一郎先生は、「実は膨大なものに依存しているのに、“私は何にも依存していない”と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状態なのだろうと思います。
だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。」と述べています。

この視点から考えると、依存は決して悪いことではなく、むしろ多様な依存先を持つことが自立への道であると言えます。
特に、障害や認知症のある方々の場合、依存先が配偶者や子供などの身内に限られていることが多いため、身内以外の依存先を増やすことが重要です。
友人、職場や地域、趣味を通じたつながり、ケアマネジャーや訪問看護師、医師、デイサービスなど、多様な依存先を持つことで、より豊かな生活を送ることができるでしょう。
もし、認知症に関してどこに頼っていいかわからないという方は、ぜひ地域の認知症の人と家族の会にお問い合わせください。
受診を希望される場合は、当院へのお問い合わせも大歓迎です。

依存と依存症は異なる
一方で、「依存症」となると話は異なります。
依存症とは、特定の物質や行為に対して、「やめたい」と思ってもやめられない状態を指します。
少し専門的な話になりますが、依存症と判断する際には、精神依存の有無が重要な指標となります。
精神依存とは、使用していない状態で「ほしい」と強く感じる渇望や、「今は使うべきではない」と理解していても使用してしまうコントロール障害を呈する状態を指します。
依存症の代表的な例として、アルコール依存症や違法薬物の依存症をイメージされる方が多いかもしれませんが、近年では市販薬の依存症やゲーム依存症なども社会問題となっています。
依存症には背景がある
以前は、依存症はパーソナリティの問題や意志の弱さと関連付けられることが多く、診断分類の中でもパーソナリティ障害の一部として位置付けられていました。
しかし、近年では「自己治療仮説(Self-Medication Hypothesis)」が提唱され、依存症の背景にある心理的な課題に注目が集まっています。
この仮説によれば、人々は不安や痛み、苦痛を和らげるために、物質や行為に依存するようになるとされています。
例えば、ストレスやトラウマを抱える人が、その苦痛を軽減する手段としてアルコールや薬物に手を出し、結果として依存症に陥るケースがこれに該当します。
したがって、依存症の治療や支援においては、単に物質や行為の使用を止めさせるだけでなく、その背景にある心理的な苦痛や問題に目を向け、適切なケアを提供することが重要です。

早めに
以上のように、依存と依存症は明確に区別されるべき概念です。
前者は人間が生きていく上で自然なものであり、多様な依存先を持つことは自立や豊かな生活につながります。
一方、後者は個人や周囲の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期の介入と適切な支援が必要です。
依存症におちいる方は社会的に孤立していることが多いことでも知れられています。
依存症に関する理解を深め、偏見をなくし、支援の手を差し伸べて繋がりを作っていくことが、社会全体の課題であると言えるでしょう。
「依存」と聞くと、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか。
もしかすると、ネガティブな印象を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。
デジタル大辞泉によれば、「依存」とは「他に頼って存在、または生活すること」と定義されています。実際、私たちは日常生活の中で多くのものに依存しています。
例えば、私はこの原稿を書くのにパソコンを使っていますし、視力が低いためメガネをかけています。
原稿のやり取りはメールを利用し、執筆中にはインターネットで調べ物をしています。
これらはすべて、私がさまざまなツールや技術に依存している例です。
依存と自立は対立しない
障害者研究の第一人者である熊谷晋一郎先生は、「実は膨大なものに依存しているのに、“私は何にも依存していない”と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状態なのだろうと思います。
だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。」と述べています。

この視点から考えると、依存は決して悪いことではなく、むしろ多様な依存先を持つことが自立への道であると言えます。
特に、障害や認知症のある方々の場合、依存先が配偶者や子供などの身内に限られていることが多いため、身内以外の依存先を増やすことが重要です。
友人、職場や地域、趣味を通じたつながり、ケアマネジャーや訪問看護師、医師、デイサービスなど、多様な依存先を持つことで、より豊かな生活を送ることができるでしょう。
もし、認知症に関してどこに頼っていいかわからないという方は、ぜひ地域の認知症の人と家族の会にお問い合わせください。
受診を希望される場合は、当院へのお問い合わせも大歓迎です。

依存と依存症は異なる
一方で、「依存症」となると話は異なります。
依存症とは、特定の物質や行為に対して、「やめたい」と思ってもやめられない状態を指します。
少し専門的な話になりますが、依存症と判断する際には、精神依存の有無が重要な指標となります。
精神依存とは、使用していない状態で「ほしい」と強く感じる渇望や、「今は使うべきではない」と理解していても使用してしまうコントロール障害を呈する状態を指します。
依存症の代表的な例として、アルコール依存症や違法薬物の依存症をイメージされる方が多いかもしれませんが、近年では市販薬の依存症やゲーム依存症なども社会問題となっています。
依存症には背景がある
以前は、依存症はパーソナリティの問題や意志の弱さと関連付けられることが多く、診断分類の中でもパーソナリティ障害の一部として位置付けられていました。
しかし、近年では「自己治療仮説(Self-Medication Hypothesis)」が提唱され、依存症の背景にある心理的な課題に注目が集まっています。
この仮説によれば、人々は不安や痛み、苦痛を和らげるために、物質や行為に依存するようになるとされています。
例えば、ストレスやトラウマを抱える人が、その苦痛を軽減する手段としてアルコールや薬物に手を出し、結果として依存症に陥るケースがこれに該当します。
したがって、依存症の治療や支援においては、単に物質や行為の使用を止めさせるだけでなく、その背景にある心理的な苦痛や問題に目を向け、適切なケアを提供することが重要です。

早めに
以上のように、依存と依存症は明確に区別されるべき概念です。
前者は人間が生きていく上で自然なものであり、多様な依存先を持つことは自立や豊かな生活につながります。
一方、後者は個人や周囲の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期の介入と適切な支援が必要です。
依存症におちいる方は社会的に孤立していることが多いことでも知れられています。
依存症に関する理解を深め、偏見をなくし、支援の手を差し伸べて繋がりを作っていくことが、社会全体の課題であると言えるでしょう。
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。