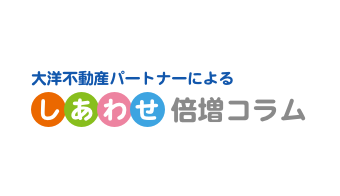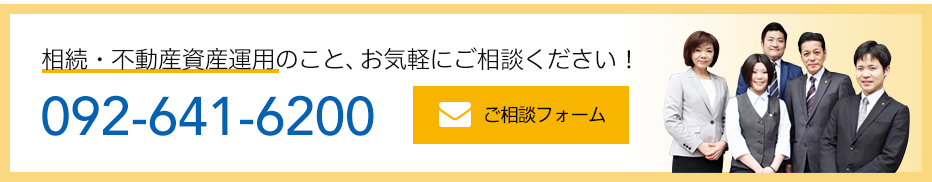2025/08/10
本当に「米国株一択」でいいんですか?~今こそ長期視点で立ち止まるべき理由
ここ数年、米国株人気が加速しています。
特に新NISAの開始以降、「とりあえずS&P500に積み立て」という流れは、まるで“国民的ルール”のようになりつつあります。
確かに、これまでのパフォーマンスを見る限り、米国株が「正解」に見えるのは無理もありません。
でも 本当にそれでいいのでしょうか?
ゴールドマン・サックスが出した、気になる見通し
昨年秋に、Bloombergが報じたゴールドマン・サックスのレポートによると、S&P500の今後10年の年率トータルリターンはわずか3%程度にとどまる可能性があるといいます。
過去10年間の平均リターンは13%、長期平均でも11%だったことを考えると、かなりの減速です。
さらに注目すべきは、次の2点。
・S&P500が米国債を下回る可能性:約72%
・S&P500が今後10年のインフレ率を下回る可能性:約33%
つまり、「米国株に投資していれば長期的に報われる」という前提が、これからの10年では崩れる可能性があるということです。
データが示す「高PER=低リターン」の現実
以下のグラフをご覧ください。
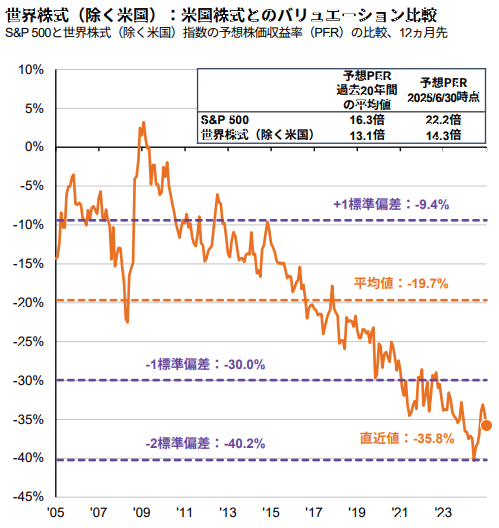
データ出所:JPモルガン・アセット・マネジメント「guide-to-the-markets-jp2025.3Q」
今年6月末時点のS&P500の予想株価収益率(PER)は22倍を超えており、米国株は米国以外の国(14.3倍)と比べて明らかに割高です。
そして、過去のデータから見ると、現在のようなPERが高いタイミングで投資を始めた場合、10年後のリターンはほぼゼロかマイナスにとどまっています。
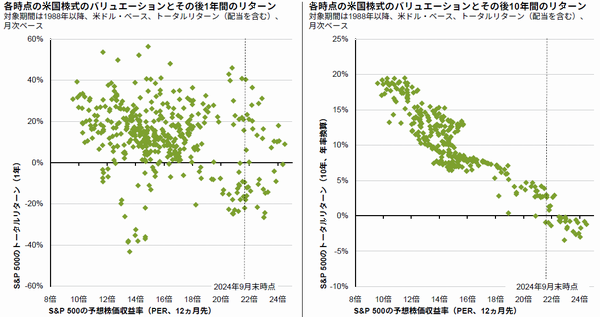
データ出所:JPモルガン・アセット・マネジメント「guide-to-the-markets-jp2024.4Q」
短期で見れば値動きは予測できませんが、10年スパンで見ると「割高な時期に買う=将来のリターンが小さい」という相関は極めて強いのです。
投資において大切なのは、「高値掴み」をしないこと
どんなに強い市場であっても、買うタイミングを間違えれば長期で報われにくくなります。
今の米国株(S&P500)の水準は、過去と比べても明らかに“高値圏”にあります。
「投資信託を毎月積み立てているから関係ない」という声もあるかもしれません。
確かにドルコスト平均法の効果はある程度期待できますが、それでも最初に高値で買い始めた場合、最終的なリターンに影響するのは避けられません。
慎重になるべき理由は、それだけで十分にあります。
日本人の「米国株一極集中」に潜むリスク
投資というのは、本来「分散」が基本のはずです。
ところが、最近の日本人投資家の動きを見ると、「米国株こそ正義」とばかりに、全資産をS&P500やNASDAQに集中させているケースが目立ちます。
この背景には、SNSやメディアの影響、新NISA制度の設計(特定のインデックスファンドへの誘導構造)など、様々な要因があると思います。
しかし、冷静に見れば今の米国株は、世界全体の中でも特にバリュエーションが高く、逆に米国以外の株式市場はかなり割安に放置されています。
たとえば、米国株とそれ以外の世界株のPER格差は直近で**−35.8%**と、過去20年間でも最大級の水準です。
これほどまでに割安な地域を無視して、ひとつの市場にすべてを賭ける戦略が本当に合理的でしょうか?

結論:今こそ「立ち止まる勇気」を持つとき
「迷ったら米国株」という考え方が通用した時代は、ひとまず一区切りがついたのかもしれません。ゴールドマンの予測や各種データは、その可能性を強く示唆しています。
もちろん米国の経済力や企業の競争力は依然として高く、今すぐ全面撤退すべきという話ではありません。ただ、投資の基本はあくまで“安く買って長く持つ”こと。
その観点から今の米国株市場を見たとき、「買い場」だと断言するには、やや慎重になるべき状況だと言えるでしょう。
焦らず、冷静に。
長期投資こそ、腰を据えて考えるべきです。
ここ数年、米国株人気が加速しています。
特に新NISAの開始以降、「とりあえずS&P500に積み立て」という流れは、まるで“国民的ルール”のようになりつつあります。
確かに、これまでのパフォーマンスを見る限り、米国株が「正解」に見えるのは無理もありません。
でも 本当にそれでいいのでしょうか?
ゴールドマン・サックスが出した、気になる見通し
昨年秋に、Bloombergが報じたゴールドマン・サックスのレポートによると、S&P500の今後10年の年率トータルリターンはわずか3%程度にとどまる可能性があるといいます。
過去10年間の平均リターンは13%、長期平均でも11%だったことを考えると、かなりの減速です。
さらに注目すべきは、次の2点。
・S&P500が米国債を下回る可能性:約72%
・S&P500が今後10年のインフレ率を下回る可能性:約33%
つまり、「米国株に投資していれば長期的に報われる」という前提が、これからの10年では崩れる可能性があるということです。
データが示す「高PER=低リターン」の現実
以下のグラフをご覧ください。
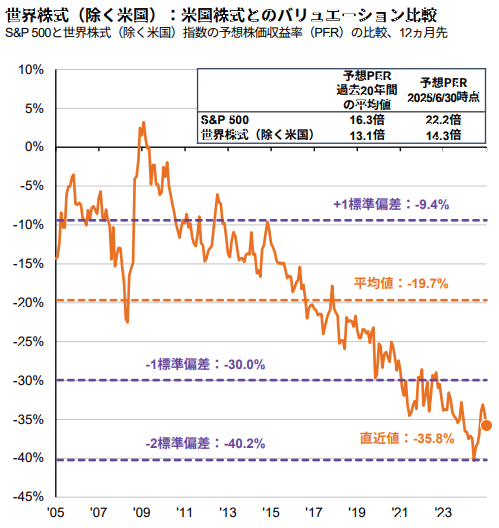
データ出所:JPモルガン・アセット・マネジメント「guide-to-the-markets-jp2025.3Q」
今年6月末時点のS&P500の予想株価収益率(PER)は22倍を超えており、米国株は米国以外の国(14.3倍)と比べて明らかに割高です。
そして、過去のデータから見ると、現在のようなPERが高いタイミングで投資を始めた場合、10年後のリターンはほぼゼロかマイナスにとどまっています。
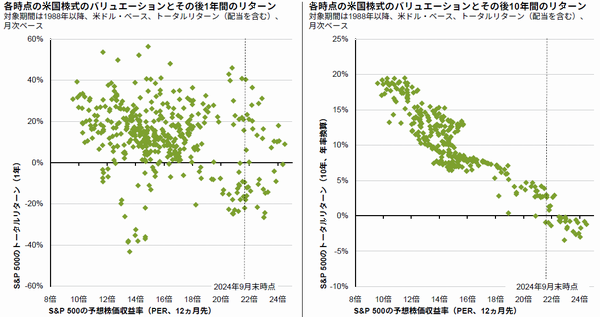
データ出所:JPモルガン・アセット・マネジメント「guide-to-the-markets-jp2024.4Q」
短期で見れば値動きは予測できませんが、10年スパンで見ると「割高な時期に買う=将来のリターンが小さい」という相関は極めて強いのです。
投資において大切なのは、「高値掴み」をしないこと
どんなに強い市場であっても、買うタイミングを間違えれば長期で報われにくくなります。
今の米国株(S&P500)の水準は、過去と比べても明らかに“高値圏”にあります。
「投資信託を毎月積み立てているから関係ない」という声もあるかもしれません。
確かにドルコスト平均法の効果はある程度期待できますが、それでも最初に高値で買い始めた場合、最終的なリターンに影響するのは避けられません。
慎重になるべき理由は、それだけで十分にあります。
日本人の「米国株一極集中」に潜むリスク
投資というのは、本来「分散」が基本のはずです。
ところが、最近の日本人投資家の動きを見ると、「米国株こそ正義」とばかりに、全資産をS&P500やNASDAQに集中させているケースが目立ちます。
この背景には、SNSやメディアの影響、新NISA制度の設計(特定のインデックスファンドへの誘導構造)など、様々な要因があると思います。
しかし、冷静に見れば今の米国株は、世界全体の中でも特にバリュエーションが高く、逆に米国以外の株式市場はかなり割安に放置されています。
たとえば、米国株とそれ以外の世界株のPER格差は直近で**−35.8%**と、過去20年間でも最大級の水準です。
これほどまでに割安な地域を無視して、ひとつの市場にすべてを賭ける戦略が本当に合理的でしょうか?

結論:今こそ「立ち止まる勇気」を持つとき
「迷ったら米国株」という考え方が通用した時代は、ひとまず一区切りがついたのかもしれません。ゴールドマンの予測や各種データは、その可能性を強く示唆しています。
もちろん米国の経済力や企業の競争力は依然として高く、今すぐ全面撤退すべきという話ではありません。ただ、投資の基本はあくまで“安く買って長く持つ”こと。
その観点から今の米国株市場を見たとき、「買い場」だと断言するには、やや慎重になるべき状況だと言えるでしょう。
焦らず、冷静に。
長期投資こそ、腰を据えて考えるべきです。
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。