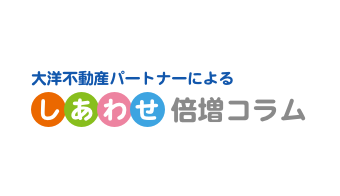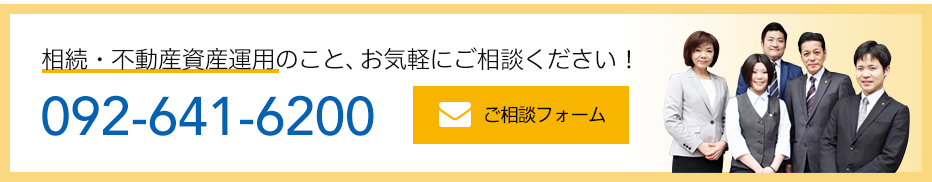2025/02/10
第17回 書籍「早合点認知症」のご紹介
認知症に対する誤解
こちらのコラムでもこれまで、認知症フレンドリーに関する取り組みをいくつか紹介してきました。私自身、認知症フレンドリーなまちづくりに関わる中で、大きな障壁となっているのが認知症のイメージが悪すぎることだと感じています。
認知症のイメージが悪いと、認知症と診断されることを恐れて認知症の診断が遅れ、認知機能障害による生活上の失敗が増えてしまうことで引きこもるようになります。
認知症予防の記事でも書きましたが、引きこもることで認知症の進行は加速してしまうのです。

なんとか認知症の悪いイメージを変える必要があるという課題感を持っていた中で、今回サンマーク出版さんからお声掛けいただき、一般の方向けの書籍を出版することになりました。
書籍タイトルは「早合点認知症」というもので、認知症に関する一般的な早合点について、正しい情報を知ってもらうことを目的としています。
内容について少し紹介をさせてください。
専門医としての視点をベースに、読みやすくていねいに
第1章では
”認知症あるある「誤解」と「勘違い」”として、「認知症=アルツハイマー型認知症」や「物忘れ=認知症」、「としのせいだから仕方ない」といったよくある勘違いや、「加齢に伴う物忘れ」と「認知症に伴う物忘れ」違いについての説明、記憶の特徴を生かしたメモの工夫、なぜ「さっきも言ったでしょ」が通じないのか、認知症を進行させてしまう「環境」について、医師・医療や介護のプロにも起こる早合点などについて解説しています。
第2章では
”「治せる認知症」を見逃すな”として、見逃されやすい治せる認知症の詳細について紹介し、さらに認知症に重なることで認知症を悪化させる疾患や状態についても解説しています。

第3章のタイトルは
”認知症の「予防」と「病院へのかかり方」”です。
多くの方が興味を持つ認知症予防について解説した上で、認知症を疑った場合にどこを受診したら良いのか、病院ではどんな検査を受けることになるのか、4大認知症についての解説などを行っています。
備える認知症へと変わる「新しい認知症観」
第4章は
”知っておきたい「軽度認知障害」と「若年性認知症」”です。
軽度認知障害(MCI)だけでなく、最近専門医の中で注目されている「主観的認知機能低下(SCD)」についても紹介しています。
さらに、若年性認知症についての解説や、必要な支援、進行を遅らせるためにできることについても解説しています。
第5章は
「認知症の治療と暮らしの支援」です。
認知症の薬についての説明や、BPSDや周辺症状と呼ばれる認知症に伴う行動障害や精神症状についての解説、「ほどよい」支援とは何かについて書いています。
最後の第6章は
「認知症フレンドリー社会へ」としました。
現状の「認知症対処社会」から「認知症フレンドリー社会」へアップデートする必要について説明を行い、さらに認知症フレンドリーテックの具体例についても紹介しています。
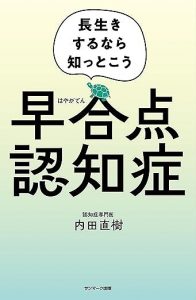
表紙は、亀をあしらいグリーンが基調となっています。
これは、当院に併設する重度認知症デイケアが「うみがめ」という名称であることや、亀が長生きを象徴し縁起がいいとされていることなどからデザインしてもらいました。
この記事が出る頃にはお近くの書店にも並んでいることと思います。
詳しい情報は、こちらの出版社サイトをご覧ください。
ぜひ、多くの方に読んでいただき、認知症の早合点を改めていただきたいと思います。
認知症に対する誤解
こちらのコラムでもこれまで、認知症フレンドリーに関する取り組みをいくつか紹介してきました。私自身、認知症フレンドリーなまちづくりに関わる中で、大きな障壁となっているのが認知症のイメージが悪すぎることだと感じています。
認知症のイメージが悪いと、認知症と診断されることを恐れて認知症の診断が遅れ、認知機能障害による生活上の失敗が増えてしまうことで引きこもるようになります。
認知症予防の記事でも書きましたが、引きこもることで認知症の進行は加速してしまうのです。

なんとか認知症の悪いイメージを変える必要があるという課題感を持っていた中で、今回サンマーク出版さんからお声掛けいただき、一般の方向けの書籍を出版することになりました。
書籍タイトルは「早合点認知症」というもので、認知症に関する一般的な早合点について、正しい情報を知ってもらうことを目的としています。
内容について少し紹介をさせてください。
専門医としての視点をベースに、読みやすくていねいに
第1章では
”認知症あるある「誤解」と「勘違い」”として、「認知症=アルツハイマー型認知症」や「物忘れ=認知症」、「としのせいだから仕方ない」といったよくある勘違いや、「加齢に伴う物忘れ」と「認知症に伴う物忘れ」違いについての説明、記憶の特徴を生かしたメモの工夫、なぜ「さっきも言ったでしょ」が通じないのか、認知症を進行させてしまう「環境」について、医師・医療や介護のプロにも起こる早合点などについて解説しています。
第2章では
”「治せる認知症」を見逃すな”として、見逃されやすい治せる認知症の詳細について紹介し、さらに認知症に重なることで認知症を悪化させる疾患や状態についても解説しています。

第3章のタイトルは
”認知症の「予防」と「病院へのかかり方」”です。
多くの方が興味を持つ認知症予防について解説した上で、認知症を疑った場合にどこを受診したら良いのか、病院ではどんな検査を受けることになるのか、4大認知症についての解説などを行っています。
備える認知症へと変わる「新しい認知症観」
第4章は
”知っておきたい「軽度認知障害」と「若年性認知症」”です。
軽度認知障害(MCI)だけでなく、最近専門医の中で注目されている「主観的認知機能低下(SCD)」についても紹介しています。
さらに、若年性認知症についての解説や、必要な支援、進行を遅らせるためにできることについても解説しています。
第5章は
「認知症の治療と暮らしの支援」です。
認知症の薬についての説明や、BPSDや周辺症状と呼ばれる認知症に伴う行動障害や精神症状についての解説、「ほどよい」支援とは何かについて書いています。
最後の第6章は
「認知症フレンドリー社会へ」としました。
現状の「認知症対処社会」から「認知症フレンドリー社会」へアップデートする必要について説明を行い、さらに認知症フレンドリーテックの具体例についても紹介しています。
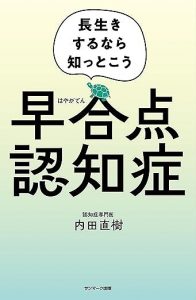
表紙は、亀をあしらいグリーンが基調となっています。
これは、当院に併設する重度認知症デイケアが「うみがめ」という名称であることや、亀が長生きを象徴し縁起がいいとされていることなどからデザインしてもらいました。
この記事が出る頃にはお近くの書店にも並んでいることと思います。
詳しい情報は、こちらの出版社サイトをご覧ください。
ぜひ、多くの方に読んでいただき、認知症の早合点を改めていただきたいと思います。
すべての著作権は(株)大洋不動産に帰属しています。無断転載は固くお断りいたします。